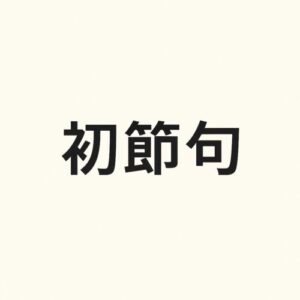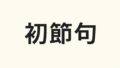初節句、何もしないってアリ?後悔しないために大切なこと
「初節句、何もしてあげられなかった…」そんなふうに悩むママやパパも少なくありません。でも実は、初節句を何もしない家庭もたくさんあるんです。「忙しくて準備できなかった」「周囲に気を遣いすぎて疲れてしまった」など、理由はそれぞれ。でも共通しているのは、“家族の形に合わせた選択をした”ということ。
初節句は、必ずしも盛大に祝わなければならないものではありません。気持ちがこもっていれば、どんな形でもOK。だからこそ、「何もしなかった」ことを不安に思う必要はないんです。
それでは、さらに詳しく説明していきますね!😊
初節句とは何か
初節句とは、赤ちゃんが生まれて初めて迎える節句のこと。男の子は5月5日の「端午の節句」、女の子は3月3日の「桃の節句(ひなまつり)」が対象です。この日は、子どもの健やかな成長を願ってお祝いをする風習ですが、実は家庭ごとにお祝いの仕方はさまざま。必ずしも盛大に祝わなければならない決まりはありません。現代では、「無理せず自分たちのペースで」と考える家庭も増えています。
初節句を何もしない人の理由
「初節句、結局何もしなかった」という声は、意外と多いんです。理由としては、「仕事や育児が忙しくて準備する余裕がなかった」「家族の都合が合わなかった」「お宮参りやお食い初めと近くて負担が大きい」など、生活事情がほとんど。中には、「子どもがまだ小さくてイベントを楽しめる年齢じゃないし」と判断するママやパパも。特に第一子だと、初めてのことに戸惑う人も多く、お祝いを見送る家庭も自然と出てきます。
初節句を何もしなくても大丈夫?
結論から言うと、何もしなくても全く問題ありません。大切なのは「お祝いの形」ではなく、「お祝いしたいという気持ち」。たとえイベントを開かなくても、心の中で願っていれば十分なんです。実際に、何年も経ってから「そういえばやらなかったね」と笑い話になる家庭も。お祝いを義務のように感じてストレスになるくらいなら、やらない選択をしてもOK。無理に人と比べる必要はありませんよ。
初節句をしなかった人の体験談
「初節句、正直なところ何もしませんでした。でも、それでよかったと思っています。」という声は少なくありません。あるママは、実家が遠方で両親を呼べなかったため、あえて行事としては何もせず、家族3人で静かに過ごしたそうです。また、別の家庭では「お金も時間も足りなくて、写真だけ撮って終わり。でも、今振り返っても全然後悔していない」と話していました。どの体験談にも共通するのは、無理をしなかったことで気持ちに余裕が持てたという点です。
初節句をしないことで後悔する?
後悔するかどうかは、本当に人それぞれです。中には「SNSで他の家族の初節句の様子を見て、やっぱり何かすればよかったかな…」と感じたママも。一方で、「記念写真すら撮ってなかったけど、まったく気にならない」という声もありました。要は、周囲と比べてしまうと後悔につながりやすいということ。逆に、自分たちのペースで選んだ結果であれば、後悔はあまり生まれない傾向があります。後になって気になるようなら、次の年にちょっとしたお祝いをするのもアリですよ。
初節句は誰のためにするのか
初節句はもちろん子どもの成長を祝う行事ですが、実は親や祖父母の「お祝いしたい気持ち」を形にするイベントでもあります。そのため、「やらなかった」と聞くと、少しがっかりするおじいちゃん・おばあちゃんがいるのも事実。ただ、無理に相手の期待に応える必要はありません。今は「家族それぞれの形」が大切にされる時代。大切なのは、「誰のため」というよりも、「何を大切にしたいか」。子どもの笑顔を思い浮かべながら、自分たちらしい答えを見つけてくださいね。
両親・祖父母との関係性
初節句を「何もしない」と決めた場合、気になるのが両親や義両親との関係です。特に、昔ながらの風習を大切にしている世代からすると、「お祝いしないなんて非常識」と感じることもあるようです。ですが、今は家庭の事情も多様化しています。体調や経済的な理由、小さい子どもの育児中など、理由をきちんと伝えれば、理解してもらえることがほとんどです。大切なのは“やらない理由”を丁寧に説明すること。それだけで、関係性がギクシャクすることを避けられますよ。
SNSとの比較で感じるプレッシャー
SNSにあふれる「素敵な初節句」の投稿を見て、「うちは何もしてない…」と落ち込む人も多いんです。でも、SNSは“映える一瞬”だけを切り取った世界。実際の準備や大変さは写っていませんし、それが家族の幸せの全てでもありません。他人と比べるよりも、「自分の家にとって心地いいスタイル」を見つけることの方がずっと大切。SNSは参考程度にとどめて、自分の気持ちを優先してOKです。
初節句をしない時の言い訳・伝え方
もし親戚や友人に「初節句どうするの?」と聞かれて困ったら、無理に取り繕う必要はありません。「今年は体調優先で静かに過ごすことにしたんです」「お祝いは少し落ち着いてから考える予定です」と、前向きな言い方をすれば、角も立ちません。何もしないことが“悪”ではなく、家族のための“選択”だと伝えれば、理解してもらいやすくなりますよ。言い訳というより、“自分たちのペース”を伝える言葉にしましょう。
何もしない場合のメリット・デメリット
初節句をあえて「何もしない」と決めることにも、ちゃんとメリットとデメリットがあります。
- メリット:準備や費用、日程調整の負担がなく、家族のペースで過ごせる。子どもが理解できる年齢になってから改めて祝える。
- デメリット:周囲の目が気になったり、後から「やっておけばよかった」と思う可能性がある。
ただし、それも「自分たちで選んだ結果」として受け止めていれば、後悔にはつながりにくいです。大切なのは、納得して選ぶことなんです。
自分たちらしい選択とは
初節句に限らず、育児イベントは「こうするべき」という正解がないもの。だからこそ、自分たちの価値観やライフスタイルに合った選択をすることが大切です。「何もしない」という決断も、立派な“自分たちらしいお祝いの形”。記念日をどう過ごすかよりも、その日を家族でどう感じるかが一番大切です。形式より気持ちを優先して、「これがうちの形だね」と笑える選択をしていきましょう。
初節句を何もしないという選択、後悔しないために大切なこと【まとめ】
初節句を「何もしない」と決めることは、決して間違いではありません。大切なのは、「なぜそうしたか」に納得できているかどうか。ここでは、この記事で紹介したポイントを振り返ります。
✅ 理由
- 忙しさや経済的事情など、生活に無理があったため
- 赤ちゃんがまだ小さく、行事を楽しめる年齢ではなかった
- 他の行事(お宮参り・お食い初め)との兼ね合いもあり、負担を避けた
- 家族だけで静かに過ごすことを大切にしたかった
✅ 具体例
- 体験談①:写真だけ撮ってお祝いの代わりにした家庭
- 体験談②:祖父母への説明を丁寧にして、理解を得た家庭
- 体験談③:SNSでの比較から不安になったが、結果的に後悔しなかった
✅ 結論
- 「何もしない」ことも、立派な家族の選択肢のひとつ
- 他人と比べず、自分たちにとっての最適な形を選ぶことが大切
- 初節句は“お祝いの気持ち”があれば、どんな形でも◎
✅ 第三者目線でひとこと
今は、家族ごとに価値観もライフスタイルも違う時代。形式よりも、「どう過ごしたか」「どんな気持ちだったか」が思い出になります。周囲の声やSNSに流されすぎず、“自分たちらしい初節句”を選べたなら、それがいちばん幸せな形ですよ😊